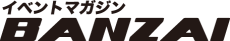宇多田ヒカル、2016年を代表する1枚となった復帰作
昨年9月にリリースされたアルバム『Fantôme』は、宇多田ヒカル8年振りの復帰作にして、昨年の音楽シーンを代表する1枚といえるアルバムになった。そして日本はもとより海外でも画期的なチャートアクションを記録し、(あくまで作品性ではなくセールスとして)村上春樹の新刊のようなロングセラーとして、現在も売上を更新し続けている。新春に際し、多くのリスナーに迎え入れられたこの傑作の魅力を、本人の発言を交えながらあらためて検証してみる。Text:内田正樹

2016年を代表する1枚となった復帰作。いまあらためて考察するヒットの理由
2017年迎春。おそらく本稿が読まれている頃には、宇多田ヒカルが第67回NHK紅白歌合戦への出演を無事に終えていることだろう。
「こんなアルバムはもう二度と作れないと思う」
〔※ここからの宇多田の発言は(別途出典記載を除き)筆者が担当したアルバムリリース時のオフィシャルインタビューから抜粋〕。
宇多田自身がこう語っていた通り、昨年9月28日にリリースされた約8年振り6枚目のオリジナルアルバム『Fantôme』は、彼女のキャリアにおいて殊更に重要な作品であり、2016年の音楽シーンを語る上で欠かせない一枚となった。約6年間の“人間活動”による音楽活動休止中、最愛の母の逝去、再婚、第一子の出産といった人生の一大事を経験した彼女は、あらためて音楽と向き合うにあたり、復帰作を母へ捧げようと決意した。
「アルバム制作の過程でぐちゃぐちゃだった気持ちがだんだんと整理されていった。『母の存在を気配として感じるのであればそれでいいんだ。私という存在は母から始まったんだから』と思えるようになった」
こうして誕生したアルバムのリードトラック「道」は、前述の出来事を経た彼女の率直な想いが凝縮された宣誓のような曲となった。古くはジョン・レノン、近年ならアデルやビヨンセなど、アーティストが自身の人生の重要な局面を歌ったアルバムはこれまでにも多々あったし、もちろん邦楽においてもそうした楽曲は存在する。
だが日本のCDセールス記録保持者である彼女のような第一線のアーティストが、自らレクイエムだと公言してアルバムを発表したような事例は他に思い当たらない。その上で、しかも本作はいくばくかのエロス(性)とタナトス(死)を内包しながらも、最終的にはそれを凌駕するほどのポジティヴィティ(生)を多くのリスナーにもたらすポテンシャルを秘めた、破格のポップアルバムだったのだ。
実際、本作の全11曲にはリスナーの生活における多様なシチュエーションに適応するリリックが散見できる。例えば前述の「道」は、両親をはじめとする家族や恩人、恋人など、今はもう会わない、もしくは会うことの叶わない人への想いなど、様々な受け取り方が出来る。
これは「花束を君に」や「真夏の通り雨」やその他の曲でも同様である。また片思いの恋慕を思わせる「ともだち」は、リリース後のテレビ番組出演時に、宇多田自身の口から「同性愛者による同性愛者ではない友達への恋を歌った曲」だと語られた。
類い稀なソングライティングの才が、多くのリスナーと共通できる幾つものメタファーを備えたポップスへと極めて美しい結実を迎えた。このあたりに、まず『Fantôme』が多様性の時代を生きる多くのリスナーに支持された理由の一端があるように思える。
互いの特性が共鳴した豪華ゲスト陣
時代にまつわる考察としては、本作に参加したゲスト陣からも幾つかの事柄が読み解ける。日英の生楽器のミュージシャンと3組のゲストを招き入れ、宇多田のキャリア史上、最も“開かれた”レコーディングが行われた点も『Fantôme』の特徴だった。「ともだち」に参加した小袋成彬(OBKR)はインディーズのレーベル “Tokyo Recordings” を主宰している気鋭のアーティストである。そして「忘却」で宇多田をリードする役を務めたKOHHもまた独自のスタンスで活動を続けている注目のラッパーであり、本作のリリース直前にはフランク・オーシャンの新作への参加というトピックでも注目を集めた。
無論オファーの動機は音楽性そのものだったが、宇多田の音楽をリスナーとして思春期に体験した世代である彼らとの共演は、結果として彼女と彼らの双方に共通する“独立性”、“独自性”、“ボーダレス”、“ジャンルレス”といった特性の共鳴にも繋がった。
さらにデビュー同期(1998年)組の椎名林檎との共演である。「日常と非日常の危うい関係を表現したかった」と宇多田が語った「二時間だけのバカンス」はミュージックビデオも制作され、リスナーは伝説の“東芝EMIガールズ”再結成をビジュアルからも堪能することができた。母として、妻として、ひとりの女性としてシンパシーを抱く者同士のデュエットは、盟友の復帰作に絶大なインパクトとプレジャーをもたらした。
椎名は昨年のリオ五輪閉会式におけるフラッグハンドオーバーセレモニー(引き継ぎ式)で音楽監修を務め、全体の演出にも大きく貢献した。宇多田が活動を再開させた2016年は、奇しくも椎名にとっても自らのキャリアに新たな1ページを刻んだ年となったのだ。デビュー当時からJ-POPというカテゴライズに捉われず(というかむしろそこから距離を置いて)活動してきた2人のこうした再会のタイミングに、偶然ではなく必然のようなドラマを感じたリスナーも少なくなかったはずだ。
純粋に“音楽”が評価された海外チャート
『Fantôme』はオリコンのデイリーとウイークリーチャートで初登場1位を獲得した。これは彼女のオリジナルアルバムとしてはデビューアルバムの『First Love』から6連続6作目の記録となった。加えて言えば、この記録はフィジカルパッケージ(CD)では初回特典盤など複数のバージョンが見られる昨今に、あくまでも通常盤一形態による音楽のみでの勝負という、『First Love』から守ってきたポリシーを貫いた上で獲得されたものだ。そして『Fantôme』は海外でも爆発した。iTunes Music Storeでは19の国と地域で1位を獲得し、全米では日本人女性ソロアーティストとして初となる3位に輝き、33カ国でランクインを果たしたのだ。正直、この要因について筆者は十分な答えを持ち合わせていないのだが、どうやらすでに複数の音楽サイトで分析されている通り、『Fantôme』のサウンドのクオリティが、供給側の想像を超えて世界各国で評価されたという、極めて理想的なチャートアクションだったようだ。
「いまの自分には英語を使うことが“逃げ”に感じられた。だから今回は日本語で歌う意義や“唄”そのものを追求しようと決めていた」
宇多田はこうした意図から本作の制作において、自らがこだわった日本語を丁寧に伝えるべく、少ないトラックによるアレンジを念頭に置いていた。またオフィシャルインタビューでは「花束を君に」のイメージの種としてオフコースやチューリップ、エルトン・ジョンの名を、さらに近年のフェイヴァリットとしてディアンジェロやアトムス・フォー・ピースらを挙げている。つまりかつての“ニューミュージック”が備えていた歌謡性と、世界的なポップスのトレンドである緻密にしてシンプルなアレンジによるグルーヴとのハイブリッドが『Fantôme』の基礎構造なのだ。
大半の曲のレコーディングとミックスを手掛けたスティーブン・フィッツモーリス(アデルやサム・スミスの作品に参加)の貢献も大きかったが、やはり今回の海外からの反応は、作詞・作曲・アレンジ・歌唱の全てをこなす宇多田の音楽性そのものに対して送られた賞賛と捉えていいだろう。
ロングセラーとなった『Fantôme』は、いまこの瞬間も新たなリスナーを獲得しているはずだ。本作の成果は日本の後進のアーティストたちにとって、また誰よりも宇多田自身にとって、今後の希望となるだろう。だが本作の真の意義は、もう暫くの歳月を重ねた後にこそ、あらゆる意味で明らかになっていくのではないかと思えてならない。
Fantôme

ユニバーサルミュージック
TYCT-60101
¥3,240(税込)
NOW ON SALE