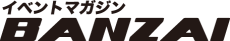【前編】a-nation 2018座談会ー avexが創りだした、音楽のテーマパーク『a-nation』の歴史に迫る
2018年の東京開催も間近に控えた『a-nation』。日本の夏フェスとして名高いa-nationの原点は93年まで遡る。そんなa-nationの歴史を紐解くべく、皆勤賞のDJ KOO氏、avex宮腰厚彦氏、シミズオクト菅谷忠弘氏に話を聞いた。観客からはわからないバックステージの話やavexだからできたこと、a-nationが果たしたダンス文化への貢献話が飛び出した。

「フェスできちゃうんじゃない?」というところからのチャレンジ
一まず最初にa-nation立ち上げのきっかけとなったことをうかがわせてください。
宮腰:大元を辿ると、東京ドームに巨大なお立ち台が出現した93年、94年の『avex rave』なんです。それが野外イべント『avex dance Matrix’95 TK DANCE CAMP』につながり、96年から2001年まではべルファ一レを中心に毎年夏のイべントを開催するようになった。CDに封入された参加券があれば誰でも入れるという、今思えば無茶苦茶な企画だったんですけど(笑)。
DJ KOO:当時誰も知らなかったTRFが、『avex rave』でいきなり東京ドームに立った。それを可能にしちゃうavexの活気や勢いを僕自身すごく感じてましたね。
宮腰:その後、avexも会社として成熟。世の中ではフェスがブームになりつつあった。そういった要素が合わさって誕生したのがa-nationだったと思うんです。
一レコード会社およびマネージメントが運営するフェスというのはレアでしたよね。
宮腰:ふと気づけばavexには多くの人気アーティス卜がいて、単純に「フェスできちゃうんじゃない?」と(笑)。そういうところからのチャレンジだったと思うんです。
DJ KOO:そこから回を重ねるごとに、a-nationは新人さんたちにとってのステイタスになっていきましたね。昼帯に出演しながら、「絶対いつかは夜帯に出る」と想いを強くし、それを実現したアーティストもいる。そんな姿にa-nationの歴史を感じます。
宮腰:象徴的なのがAAAですよね。最初何年かはトップバッターでしたが、a-nationの歴史とともにヘッドライナーにまで育った。a-nationの申し子的存在ですね。
一開催地や開催方法など、当初はいろいろなご苦労があったと思います。
宮腰:1年目は本当に手探りでした。7会場10公演で、土、日で都市をまたいで開催などスケジュールも無茶苦茶。ご苦労をまともに味わったのは菅谷さんでしょう(笑)。
菅谷:土、日それぞれに別働隊を組み、もちろんセットも2つ造って対応してましたね。移動もかなりの距離でした。土曜日は富山、日曜日は仙台、みたいな。アーティストさんたちもバス移動されてましたよね。
宮腰:はい。経済的にナンセンスなことばかりやってました(笑)。そういったある種の失敗を積み重ねて、イべントとしての完成度を上げていきましたね。今では、日本一転換の早いフェス と言われている。気づいたらー丸となってそこを追求していました。それによって出演枠も増えてるんじゃないかな。
DJ KOO:観客が暇を持て余す時間がないというのがa-nationの特徴。各部署のスタッフさんたちの工夫とご苦労の賜物ですね。
菅谷:真ん中にメインステージがあって、上手、下手にそれぞれサブ・ステージがある。こっちが終わったらあっちというふうにわずかな時間で転換ができるのは、他のフェスでは考えられない巨大なバックヤードがあって、楽器や機材がライザーの上で準偏万端で待機しているからなんですよ。
DJ KOO:バックヤードは僕らにとっては夢の世界。ミュージシャンの楽器セッティングの秘密がのぞけたりしますから。もちろん、そこにもスタッフさんがいて、自分の城を守ってるんですけどね。ステージとバックヤードを担うシミズオクトさん、音響を担うヒビノさん(ヒビノ株式会社)をはじめ、各方面のプロの方たちが、限られた時間を有効に使うために本当に努力をしてくださってます。a-nationはまさにチームワーク・フェスなんです。